高齢者の眠れない悩みと不眠症の現状
高齢者の睡眠は若い頃とは大きく異なります。
加齢に伴い、必要な総睡眠時間は短くなり、深い眠りが減少し、浅い眠りが増える傾向があります。
そのため「夜中に何度も目が覚める」「早朝に起きてしまう」といった悩みが多く見られます。
これらは必ずしも病気ではなく自然な加齢現象の場合もあります。
しかし、日中の生活に支障をきたす場合には不眠症と診断されることがあります。
不眠症と加齢による睡眠変化の違い
正常な加齢による変化
-
睡眠時間が短くなる
-
夜間の覚醒が増える
-
朝型に移行しやすい
病的な不眠症の特徴
-
入眠困難、中途覚醒、早朝覚醒が週3日以上・3か月以上続く
-
日中の生活に明確な支障をきたす
-
集中力や気分の低下、生活の質の低下が目立つ
この違いを理解することが、適切な対応の第一歩です。
高齢者の眠れない原因
生理学的要因
加齢によるメラトニン分泌の低下や体内時計の変化が、睡眠リズムを乱す原因となります。
身体疾患や精神疾患
糖尿病の頻尿や心不全、うつ病、不安障害などが不眠を引き起こします。不眠と病気が悪循環を形成することもあります。
特殊な睡眠障害
-
睡眠時無呼吸症候群(いびき・無呼吸)
-
むずむず脚症候群
-
レム睡眠行動障害
これらは専門医による診断と治療が必要です。
薬物や生活習慣
降圧薬や抗うつ薬などの副作用、また日中の活動不足、長時間の昼寝、カフェインやアルコールの摂取が不眠を悪化させます。
不眠症がもたらすリスク
身体的リスク
-
夜間の転倒や骨折
-
免疫力低下による感染症リスク増加
-
高血圧や心血管疾患のリスク上昇
認知機能への影響
慢性的な不眠はアルツハイマー型認知症と関わりが深く、記憶力や判断力の低下を加速させる恐れがあります。
心理・社会的リスク
睡眠不足による疲労感は外出や交流を減らし、社会的孤立やうつ病を招きやすくなります。
高齢者におすすめの改善方法
生活習慣の見直し
-
毎日同じ時間に起きる
-
朝日を浴びる
-
日中に軽い運動を取り入れる
-
昼寝は15時までに30分以内
-
寝室の環境を快適に整える
-
就寝前のスマホやカフェインを避ける
認知行動療法(CBT-I)
-
刺激制御法:眠くなった時だけベッドに入る
-
睡眠スケジュール法:睡眠時間を調整し効率を高める
非薬物療法は副作用がなく、安全で持続可能な改善策です。
薬物療法を選ぶときの注意点
従来の睡眠薬の問題点
ベンゾジアゼピン系や非ベンゾジアゼピン系の薬は、転倒や依存性、記憶障害のリスクがあります。
新しい世代の睡眠薬
-
メラトニン受容体作動薬(ラメルテオン)
-
オレキシン受容体拮抗薬(スボレキサント、レンボレキサント)
これらは副作用が少なく、高齢者に適しています。ただし必ず医師の指導のもとで使用すべきです。
専門医に相談すべきタイミング
-
不眠が3か月以上続いている
-
日中の生活に支障がある
-
頻尿やいびき、気分の落ち込みがある
睡眠日誌や服薬中の薬リストを準備して受診すると診断がスムーズです。
症状に応じて精神科、心療内科、耳鼻咽喉科などを選びましょう。
まとめ
眠れないと悩む高齢者の不眠症は、加齢による自然な変化から疾患や生活習慣まで、さまざまな要因が関与しています。
放置すると転倒や認知症リスク、社会的孤立といった深刻な問題を引き起こします。
まずは生活習慣の改善や認知行動療法を取り入れ、必要な場合には新しい世代の睡眠薬や専門医のサポートを受けることが大切です。
正しい対策を行うことで、生活の質を高め、健康で安心できる毎日を取り戻すことができます。


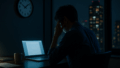
コメント