ビタミンB1とは何か
ビタミンB1は、チアミンとも呼ばれる水溶性ビタミンで、糖質の代謝や神経機能の維持に欠かせない栄養素です。
特に、私たちの体がエネルギーを作り出す際に重要な役割を果たし、不足すると疲労感や集中力の低下を招くことがあります。
ビタミンB1の働きと不足による影響
ビタミンB1は、糖質を効率よくエネルギーに変換する補酵素として働きます。
脳や神経はブドウ糖を主なエネルギー源とするため、ビタミンB1が不足すると神経炎、手足のしびれ、倦怠感、さらには脚気やウェルニッケ・コルサコフ症候群などの重篤な症状につながることがあります。
ビタミンB1を豊富に含む食べ物
ビタミンB1を摂取するには、以下のような食品が効果的です。
-
豚肉(特にヒレやモモ):100gあたり約1.3mgと含有量が高く、日常的に摂りやすい食材です。
-
玄米や全粒粉パン:精製されていない穀物はビタミンB1が豊富で、白米の約8倍の含有量があります。
-
豆類・種実類(大豆、あずき、落花生、ごまなど):植物性の供給源として優秀です。
-
魚介類(うなぎ、たらこ):動物性食品の中でも栄養価が高い食品です。
-
野菜類(枝豆、ほうれん草、ブロッコリーなど):副菜で摂取しやすいのが特徴です。
吸収率を高める食べ合わせ
ビタミンB1は水溶性で吸収効率が高くありません。
しかし、ニンニクや玉ねぎ、ニラに含まれる「アリシン」と一緒に摂ることで「アリチアミン」に変化し、吸収率が約10倍に高まります。
豚肉とニンニクの組み合わせは理にかなった栄養摂取法です。
調理法によるビタミンB1の残存率
ビタミンB1は熱に弱く、水に溶けやすい性質があります。調理法によって残存率は異なります。
-
焼く・炒める:約85%残存
-
蒸す:約70%残存
-
電子レンジ:約75%残存
-
茹でる・煮る:約55〜65%残存
栄養を無駄なく摂るためには、炒め物や蒸し料理、煮汁を活用したスープなどがおすすめです。
現代人が気をつけるべきポイント
現代の食生活は精製穀物やインスタント食品が中心になりがちで、ビタミンB1不足のリスクを高めます。
さらに、アルコールは吸収を妨げ消費量も増やすため、大量飲酒は欠乏を招きやすい要因です。
日常的にバランスの取れた食事を意識することが大切です。
まとめ
ビタミンB1は、疲労回復や神経機能維持に不可欠な栄養素です。
豚肉や玄米、豆類を意識して取り入れ、ニンニクや玉ねぎと組み合わせることで効率的に摂取できます。
調理法を工夫しながら日々の食事に取り入れることで、健康的でエネルギッシュな生活を支えることができます。

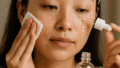

コメント