「夜ベッドに入っても眠れない」「朝まで何度も目が覚めてしまう」──。
そんな悩みを抱え、スマホで検索しているあなたへ。
実は「眠れない」は単なる寝不足ではなく、不眠症という病気かもしれません。
この記事では、眠れないときに どの診療科に行けばよいか を原因別に解説し、あわせて自宅でできるセルフケアや快眠グッズも紹介します。
不眠症とは?ただの寝不足との違い
不眠症には主に以下のタイプがあります。
-
入眠困難:寝つきが悪い
-
中途覚醒:夜中に何度も目が覚める
-
早朝覚醒:朝早くに目が覚めてしまう
-
熟眠障害:ぐっすり眠れず疲れが取れない
これらが1か月以上続き、日常生活に支障が出ている場合は、自己判断で放置せず受診を検討しましょう【参考:日本睡眠学会】。
まずは「かかりつけ医」に相談するのが安心
「眠れないけど、何科に行けばいいの?」と迷うときは、まずかかりつけ医を受診しましょう。
-
あなたの生活習慣や持病を把握している
-
必要に応じて 内科・心療内科・睡眠外来 へ紹介してもらえる
効率的に正しい治療へ進める第一歩となります。
【内科】体の病気が原因で眠れないとき
身体的な病気が眠れない原因になっている場合、内科の受診が有効です。
-
更年期障害
-
甲状腺の異常
-
高血圧・糖尿病など生活習慣病
-
薬の副作用
全国的に数が多く、受診しやすい点もメリットです。
ただし、精神的な要因が疑われる場合は心療内科や精神科に紹介されることもあります。
【心療内科・精神科】ストレスや心の不調が原因のとき
強いストレスや不安、気分の落ち込みがあるときは、心療内科や精神科が適しています。
-
心療内科:ストレスによる心身症などを中心に診療
-
精神科:うつ病・不安障害・統合失調症など幅広く対応
「最近ストレスが強い」「気分の落ち込みもある」という人は、早めに専門医へ相談しましょう。
【睡眠外来】専門的な検査が必要なとき
内科や精神科で改善しない場合や、以下の症状がある場合は睡眠外来がおすすめです。
-
睡眠時無呼吸症候群の疑い
-
むずむず脚症候群
睡眠ポリグラフ検査(PSG)など専門検査を行い、
薬物療法のほか、認知行動療法(CBT-I)やCPAP療法などを受けられます。
初診時に必要な持ち物と準備
受診をスムーズに進めるために、以下を準備しましょう。
-
健康保険証・マイナ保険証
-
紹介状(ある場合)
-
睡眠日誌(2週間以上記録)
-
就寝・起床時間
-
夜中に目覚めた回数
-
日中の眠気の有無
-
-
お薬手帳や服用中の薬の情報
さらに、「いつから眠れないのか」「生活習慣やストレス要因」も具体的に伝えると診断が正確になります。
医療機関を選ぶときのチェックポイント
-
日本睡眠学会の専門医が在籍しているか
-
睡眠障害の実績や検査設備があるか
-
自宅や職場から通いやすいか(オンライン診療も検討可)
長期的に通院する可能性があるため、通いやすさ=継続のしやすさも重要です。
不眠症の治療法とセルフケア
不眠症の治療は、以下を組み合わせて行います。
-
薬物療法(依存性が低い新しい睡眠薬も登場)
-
認知行動療法(CBT-I)
-
生活習慣の改善
セルフケアとして取り入れやすいのは:
-
規則正しい生活リズムを意識する
-
軽い運動を習慣化する
-
就寝前にリラックスする習慣をつくる
👉 自宅で取り入れやすい快眠サポートアイテム
-
【睡眠サプリ】天然成分で眠りをサポート
-
【快眠グッズ】アイマスク・耳栓で睡眠環境を整える
-
【アロマ・ハーブティー】リラックス効果で入眠をサポート
(※)
まとめ
眠れないと悩むのは自然なことですが、不眠症は治療できる症状です。
-
まずはかかりつけ医へ
-
身体の病気が疑われるなら内科
-
心の不調があるなら心療内科・精神科
-
改善しない場合や特殊症状があるなら睡眠外来
一人で悩まず、医師の診断とセルフケアを組み合わせて、健康的な睡眠を取り戻しましょう。


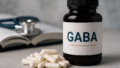
コメント